植毛するときはドナーを採取するため、後頭部を刈ります。術後は採取痕が残った頭皮がむき出しに。傷が目立たなくなり周りの既存毛が伸びてくるまではカモフラージュの対策が必要です。
手軽にできる対策のひとつであるヘアシートについて解説します。
ヘアシートとは?
ヘアシートとは聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。
ヘアシートとは、部分的なウイッグ(かつら)のこと。自毛に結び特殊な接着剤で固定をして装着します。頭皮に貼り付けるわけではありません。これを後頭部に使うことで自毛植毛後の傷跡を隠すことが出来ます。
植毛後の後頭部はかなりインパクトのある見た目となります。毛が生えそろうまでの辛抱ではあるのですが、いかんせん悪目立ちするといけないので、多くの方はヘアシートを使い隠します。使用することで植毛をしたということを周囲にバレにくくする役目を果たしているのです。これがないと採取本数が多い場合、まず間違いなく植毛したことが周囲にバレてしまうでしょう。
ただ通常の装着方法だとシートの下部が接着されないため、絶対に安全とはいえません。そのため医師などと、より自然な装着方法を相談していきましょう。
ヘアシートの取り付け期間ですが、1-3ヶ月ほどは付けておいたほうが良いとされています。ちなみにヘアシートの裏側はメッシュになっており、通気性が確保されています。蒸れるのではと心配している方も安心ですね。
ヘアシートのメリット
ヘアシート最大のメリットは言うまでもなく、術後の傷跡を違和感ないように隠すことができるという点につきます。ただ全員がヘアシート装着を希望するかというと必ずしもそうではありません。後頭部の髪が長い場合は覆い隠すことが可能です。1000グラフト未満の施術であれば使用しない方が多いようです。2000グラフト以上であると希望者は増加の傾向にあります。
後頭部を隠すという目的であれば、ウィッグの使用が全てではありません。帽子やバンダナ、タオルなどでもカバーすることができます。ただ日常生活を送るうえで、支障をきたすこともあります。公的な場面に出席するとなると、帽子を被ったままでは難しい場合もあるのではないでしょうか。採取箇所が違和感なく隠れるまで、毛が生えそろうのに数か月かかる場合もあります。周りにバレたくないという思いがある場合はヘアシート装着を希望されたほうが無難でしょう。
ヘアシートのデメリット
ヘアシート装着を希望しない方も一定数おります。一番の理由は費用です。ウィッグのような物なので安くはありません。装着と取り外しを含めると、どこのクリニックでも3-5万円前後はかかります。
また毛が伸びていくにつれ、ヘアシートの位置の調整も必要となります。自分で調整するのは難しいので、その都度クリニックに行くことになります。諸費用・交通費・時間的な捻出なども余分にかかるというわけです。少しの期間ならば我慢できるという方はヘアシートによる対策にこだわらないようです。
次に多い理由として、ヘアシートを付けたからといって周囲に完全にバレないとは言い難いからです。ヘアシートは後頭部の既存毛にしっかり装着できるため取れる心配はまずありません。しかし、自毛の色とウイッグの色合いが完璧に合うことは稀です。また髪質で違和感を感じるかもしれません。刈り上げ範囲が小さい場合や隠す手段が他にある場合は、無理に取り付ける必要はないでしょう。
まとめ
初めて植毛するという方の場合、ヘアシート装着をオススメします。というのも、自らの判断で「大丈夫」と思っても、「やっぱり最初から付けるべきでした」と後で相談に来る方が一定の割合でいるからです。
何をおいても、植毛をお願いした信頼できる医師に相談し、決めることが重要だといえるでしょう。
カテゴリー:
は | 投稿日:2019年03月29日
歳を重ねた男性の悩みと言えば薄毛。若い頃、ブリーチを使いに使い金髪をキメていたという経験のある方も多いでしょう。なかにはビジュアル系バンドのごとく立て続けにブリーチを使い、更にヘアカラー、パーマと施術するのが日常茶飯事だったという方もいるかもしれません。
そもそもブリーチの使用は薄毛の理由となり得るのでしょうか。ブリーチ剤で髪の色が変わる理由から、髪や頭皮に与えるダメージの大きさまで、ご説明いたします。
ブリーチって何?
「ブリーチって髪を金色に染める薬剤でしょ?」と思う人も多いのではないでしょうか。しかしそれは間違いです。確かに結果、髪色が金色になりますが決して染めているわけではないのです。
ブリーチとはメラニン色素を壊し脱色すること。つまり髪の毛の色素を抜くことを意味します。色を付けくわえているのではなく、黒色を除いていると説明するとしっくりくるかと思います。
 髪の色を決めるのはメラニンという色素です。メラニンにはユーメラニンとフェオメラニンの2種類があります。ユーメラニンは黒色~こげ茶色、フェオメラニンは赤茶色~黄色の色素です。髪に含まれるユーメラニンの量が多いと黒色に、少ないとこげ茶色になります。
髪の色を決めるのはメラニンという色素です。メラニンにはユーメラニンとフェオメラニンの2種類があります。ユーメラニンは黒色~こげ茶色、フェオメラニンは赤茶色~黄色の色素です。髪に含まれるユーメラニンの量が多いと黒色に、少ないとこげ茶色になります。
ブリーチはこの色素を抜くことで髪の色を変えます。茶→オレンジ→金髪と変化していくのです。
脱色の仕組み
先程説明したメラニン色素を分解すると髪が脱色されます。アンモニアなどのアルカリ剤が髪の毛のキューティクルを開きます。メラニン色素は髪の毛の内側にあるため、まずは外側にあるキューティクルを開く必要があるのです。
ブリーチの成分はアンモニアやモノエタノールなどのアルカリ剤と過酸化水素などの酸化剤です。その他の成分も入っていますが、主成分というとアルカリ剤と酸化剤になります。
髪の内側に過酸化水素が流れこみ、活性酸素を発生、メラニンを分解します。メラニンのなかでも先に黒色のユーメラニン、次に赤茶系のフェオメラニンが分解されるのです。
いきなり金色や白色にならないのには理由があったのですね。
つまり白色に近い髪にしたい場合、ブリーチ時間を長くしたり回数を増やす必要があります。
髪、頭皮に与えるダメージ
ブリーチをすると髪が傷むのはまちがいありません。キューティクルは髪の主成分のタンパク質などの栄養を保つ役割があります。それを無理矢理こじ開けるのですから当たり前ですよね。ブリーチはキューティクルを開け、更にそこに過酸化水素を流し、メラニンやケラチンを分解します。髪の毛がゴムのようになったという話も聞きますが、それは栄養が無くなったことの証左であるといえますね。
次に頭皮へのダメージですが、ブリーチ剤に含まれるアルカリ剤や酸化剤は直接頭皮を傷つけるものではありませんが、影響がないと言いきることもできないといった状態です。こちらの場合、深刻であるのがアレルギー反応があった場合です。頭皮が炎症を起こしたらただちに使用を中止しましょう。
まとめ
結論を申し上げますと、ブリーチは薄毛の直接の原因ではないといえます。ただブリーチによって頭皮環境は悪化するので、無関係ともいえません。また体質も関係するのでひとまとめにできる問題ではありません。
金髪にしたいとお考えの人も、市販製品を購入し自分でブリーチをするという方法はオススメできません。頭皮にブリーチ剤が付いてしまうからです。美容院で行った場合は美容師がブリーチ剤が根元に付かないようにしてくれますが、一人で脱色する場合はそう簡単なことではありません。頭皮に深刻なダメージを与える原因となります。また市販のブリーチは美容院で使うものより強力だといわれています。頭皮保護のためブリーチは極力美容室で行いましょう。
カテゴリー:
は,
毛髪 | 投稿日:2019年01月25日
PRP(Platelet-Rich Plasma)とは?
PRP(=Platele-Rich Plasma)は、関節炎、アキレス腱鞘炎などの治療などで近年注目を浴びている治療法である。「慢性」化してしまった患部を「急性」の状態にし、自己治癒力を高め効果を上げる治療法で、切開しない方法としてこの手術法が評価を得ている。
日本では美容整形の分野で多く利用されているが、アメリカではプロスポーツ選手へのけがの治療として遣われている。2014年にはニューヨークヤンキースの田中選手の肘の怪我の治療してPRP療法を行い知名度が上がった。
仕組み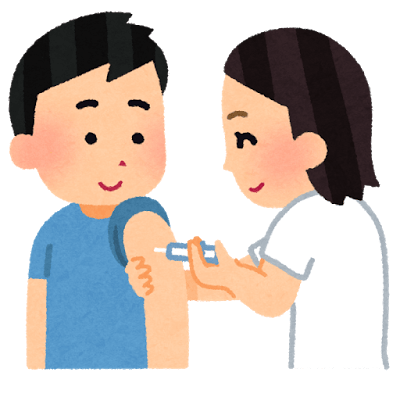
PRPとは、血小板を濃縮したものである。その中には細胞が成長しやすいよう栄養素が豊富に含まれている。治療に関して言えば、腕から採血してその遠心分離機にかけてPRP組織を抽出する。同時に針の先で患部に小さい穴をいくつか開けて新しく怪我を故意的に起こす。それにより患部にふたたび炎症を起こさせるのだ。細胞の修復には炎症は一番最初の工程であり、不可欠な過程である。栄養を豊富に含んだPRPを注入することにより治癒力を加速することができ、傷ついた幹部を再生させる。
PRP療法はリハビリなどで行っても効果のなかった慢性アキレス腱炎、足底腱膜炎などの治療法としてもみとめられている。
また、植毛時にこの治療を使用すると既存毛が濃くなるといも言われている。
カテゴリー:
は,
毛髪 | 投稿日:2016年06月14日
髪質がアフロかどうか調べる試験のこと。
その方法は鉛筆を被験者の毛髪へ通過させるというもので、簡単に判定することができる。もしペンシルが髪の毛に引っかかることなく床に落ちれば、その人物は「白人」であるとみなされた。対して引っかかった場合は、髪の毛が白人にしては縮れすぎているということになり、その人物は(人種的遺産が入り交じった)「有色人種」に分類される。有色人種とみなされた人々は、「黒人」に分類された人々よりも多くの権利を持つことが許されたが、白人に比べれば権利も義務も軽んじられた。この方法はアパルトヘイト時代に用いられており、白人、黒人、有色人種に分類される人種的アイデンティティーを測定する手段であった。1994年にアパルトヘイトが撤廃され、ペンシルテストの権威は無くなったが、南アフリカにおける文化遺産の一面であり人種主義のエンブレムであった。
 ペンシルテストの社会的影響
ペンシルテストの社会的影響
当時の人口登録法のあいまいさも手伝って、ペンシルテストの結果、多くのコミュニティが恣意的な人種的線引きのもと分裂することになる。家族であってもテストの結果から異なる人種的グループにあるとみなされ、別離を余儀なくされるケースもあった。
浅黒い肌ではあるが白人の両親をもつ少女サンドラ・ライングの例は有名である。1966年、11歳のときに「よそから来た人」にペンシルテストを受けさせられ、試験に落ちたサンドラは、その後白人だけが在籍する学校から追放されてしまった。彼女は生まれたときの人種である白人から、有色人種へと再分類されたのである。サンドラと家族は白人社会から遠ざけられた。白人の父親が実父であることは親子鑑定でも認められたものの、政府はサンドラに白人としての地位を回復することを拒んだ。彼女の生い立ちは2018年に映画化されるなどし、現代においても強い影響を与えている。
ペンシルテストの評価
アパルトヘイトの終焉した1994年にペンシルテストも終りを迎えた。しかし、依然としてこのテストは南アフリカにおける文化的な遺産の一部であり、世界的にもレイシズムの象徴であり続けた。例えば南アフリカの新聞「メール・アンド・ガーディアン」は、(黒人の)外国人に嫌疑をかけては国籍を「測定」しようとする集団が出現している状況を「21世紀のペンシルテスト」と呼んでいる。ある南アフリカのコメンテーターも同じ事件を「アパルトヘイト時代の恥ずべきペンシルテストの再現であり、おぞましい」と述べている。
2003年、ニューヨーク・タイムズの記者はこのペンシルテストを、かつて無数に行われた「人種を決定するための屈辱的な手法」のなかでも「おそらく最も馬鹿げた」ものと評した。旅行ガイドブックの「フロマーズ」にはこのテストがアパルトヘイトにおいて「最も恥ずべき人種分類試験のひとつであった」と書かれている。ほかにも「下劣」「屈辱的」「馬鹿げている」といった評価がされている。
カテゴリー:
は,
毛髪 | 投稿日:2016年03月31日
人毛で作られた毛束を毛髪に編みこむこと。付け毛の一種。髪の長さを毛束によって変えられるため、ロングヘアーにすることもできる。人毛の素材は、ファイバーで作られており超音波やボンド、シリコンキャップなどで接着している。ヘアーエクステンションはカラーも可能だが傷みやすくなるため装着後は向いていない。現在、日本で使われているものは中国やインドから輸入されて加工されたものが多い。西洋人の毛髪よりも太くハリコシの強いため日本人の髪質に合っていると言われている。ヘアーエクステンションは、傷みやすいため長持ちさせるには毎日の手入れが必要。
■シャンプーのお手入れ方法
- 水に濡らす前にエクステをブラッシングする。(汚れを落とすため)
- 頭を洗うときには上を向く。(髪を絡ませないため)
- シャンプーは頭皮を洗う(エクステのコーティングを剥がさないため)
- エクステの網目は避けて洗う。(緩み、外れを防ぐ)
- トリートメントは網目を避ける(洗い残しによる臭いの原因を防ぐ)
- トリートメントは流しすぎないようにする(エクステの乾燥を防ぐ)
■乾かし方
- 濡れたまま熱風を与えずに、まずタオルで良く水分を取る。(傷みの原因となるため)
- 洗い流さないトリートメントをつける(濡れている状態がおすすめ)
- ドライヤーは根本から(毛先が乾燥しすぎるのを防ぐ)
- 仕上げに毛先にトリートメントを付ける(乾燥から守る)
装着方法
~編み込み~
エクステンションを地毛の根元に編み込み、糸ゴムなどで縛る方法。サロンでの扱いが多く一般的にニーズが高い。
三つ編み[1] と 四つ編み の二つが編み込みの主な技法である。普通の三つ編みは技術者一人で簡単に行うことができるが、エクステンション装着の特殊三つ編み込みは熟練が必要である。四つ編み込みは通常は二人掛りで行う為、比較的容易に施術できるといったメリットがある。
編み込みは装着する一本あたりの毛量を自在に調整できたりカラーの調整が出来たりと自由度が高い、装着部の違和感は他の装着方法に比べ大きく洗髪後十分乾燥させないと装着部が臭くなったり、痒くなったりとデメリットもある。取り外しは編み込み部の糸ゴムを切れば自分で容易にできる。
~金属チップ~
直径5mm前後の金属製リング1ないし3個にエクステンションと地毛を通し、ペンチで地毛の根元に圧着する。
毛を通す量の調整が難しく毛が少なすぎて抜けてしまう、毛が多すぎて圧着の際に切れてしまうなどの事例もある。金属チップに通す毛量に制限があるため一本あたりの太さは細くなる。
取り外しは再度ペンチで金属チップを緩めて取り外す。
~接着・超音波~
何らかの接着剤を用いて地毛とエクステンションを接着する方法。
従来グルーガンと呼ばれる拳銃型の装置で、棒状の接着剤を溶かし接着するタイプが主流だったが、現在はエクステンション根元部分にケラチンまたはケラチンチップなどと呼ばれる接着剤がついた毛束をアイロンで接着するものが多い。超音波エクステと呼ばれるものも超音波アイロンで接着するので同じ方法といえる。後述する熱収縮チューブと併用して用いる場合もある。
これもやはりチップに通す毛量に制限があるため、一本あたりの太さは細くなる。接続部分が小さく目立ちにくい。
取り外しは専用の薬液で行うので自分で取り外すのは困難である。
~熱収縮チューブ~
長さ5~15mm 直径3~5mm程度の熱収縮チューブに地毛とエクステンションを通し、ヘアーアイロンでチューブを収縮させることで装着する。
熱収縮チューブは内側に接着剤が塗られており、収縮と同時に熱で溶ける仕組みのものが多い。接続部分が小さく目立ちにくい。
取り外しは専用のリムーバーで行う。
シール・テープ
装着技術の中では新しく特許関連製品である。
エクステの根元部分に粘着テープが予め付いており、取り付けにアイロンなどの器具を必要とせず取り付けがとても早い。また平面で取り付けるため装着感が良いと人気となっている。価格はやや高いがリペアして繰り返し使えるなどコストパフォーマンスは良いといえそう。最近は技術の進歩によりシール部分が薄く柔らかく長期使用できるものも出てきており今後が期待できる。自分で取り外せない物もある。
 まつ毛のエクステンションもあります。
まつ毛のエクステンションもあります。
カテゴリー:
は,
毛髪 | 投稿日:2016年03月22日
毛髪に熱を与え髪形をストレートにする道具。家庭でも毎日のスタイリングに欠かせない道具となっている。頻繁に熱を与えると髪のダメージを与える。適した温度は170℃以下だと言われている。180℃以上で何回も熱を与え続けるとキューティクルが剥がれてしまいダメージを与えてしまう。日本では、1904年に火箸を炭火で温めてヘアーアイロンのようにストレートのヘアヘアスタイルにしていた。
ヘアーアイロンを使用する際の基本と言われている温度は大体160℃から180℃である。またストレートにするタイプとカールを付けるタイプのアイロンの2種類があり使い方や温度も異なる。
~ストレートアイロン~
170℃ほどの温度で2、3秒熱を与えるのが適温。
~カールアイロン~
髪に巻きつけてから10秒ほど保持するため温度は130°が適温。
 【熱による髪へのダメージ】
【熱による髪へのダメージ】
熱によるダメージは、髪を上手にセットしづらくしてしまいます。
ヘアアイロンの熱によって及ぼされる髪へのダメージとしては、
・タンパク変性
・水蒸気爆発
・炭化現象
の3つがあげられます。
それぞれ、髪の毛にどのような働きが起こりダメージに繋がってしまうのか、詳しくみていきたいと思います。
タンパク変性
熱や化学処理によってタンパク質が変化してしまうことを指します。
髪の毛はタンパク質で形成されているので、アイロンの熱によって髪の毛が硬くなり、ダメージが進行してしまいます。
例えますと、同じタンパク質として魚や肉や卵なども、熱により変化することも同様です。髪の毛のタンパク変性は60℃から始まります。
また、110℃以上になると髪は急激に固くなります。
さらに、250℃でキューティクルは溶けてしまいます。
(※アイロンを180℃に設定した場合、長時間アイロンを髪に当てなければ、髪に伝わる熱は100℃いかないくらいです。)したがって、ヘアアイロンの温度設定と、髪に熱を当てる時間はとても大切となってくるのです。
水蒸気爆発
・薄毛、抜け毛などに髪内部の水分が蒸発することによって、髪の構成要素を破壊してしまうことを指します。
・髪のキューティクルは温度と湿気によって開き、温度は約30~60℃になると少しずつ開いていきます。
シャワーやドライヤーやアイロンをした直後は、キューティクルが開いた状態にあります。
・キューティクルが開いた状態で熱いヘアアイロンを髪にあてることで、髪の内部の水分まで蒸発させてしまうことになるのです。
すると、水蒸気爆発という現象を起こして、髪を構成している様々な要素を破壊してしまいます。
・キューティクルが開いた状態は、髪の内部の成分が外に出やすい状態ですが、反対に、栄養や薬剤などの成分が内部に入りやすい状態でもあるのです。
炭化現象
髪の毛のタンパク質が焦げてしまい灰のようになってしまうことを指します。
ヘアアイロンの熱を髪の同じところに当てすぎることによって、この炭化現象が起こります。
また、炭化してしまうと髪の毛にパーマがかかりにくくなり、カラーも色を入れても灰色っぽくなってしまいます。
カテゴリー:
は,
毛髪 | 投稿日:2016年03月22日










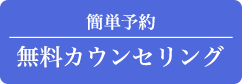
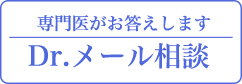
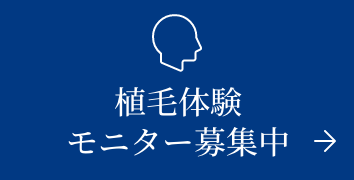
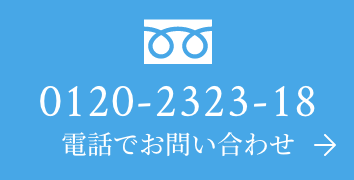
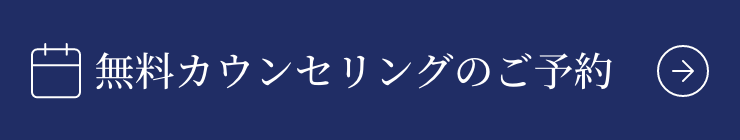
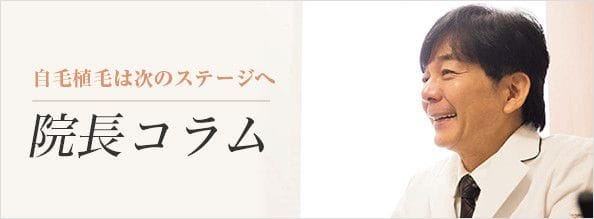


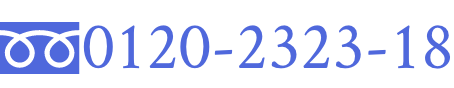
 髪の色を決めるのはメラニンという色素です。メラニンにはユーメラニンとフェオメラニンの2種類があります。ユーメラニンは黒色~こげ茶色、フェオメラニンは赤茶色~黄色の色素です。髪に含まれるユーメラニンの量が多いと黒色に、少ないとこげ茶色になります。
髪の色を決めるのはメラニンという色素です。メラニンにはユーメラニンとフェオメラニンの2種類があります。ユーメラニンは黒色~こげ茶色、フェオメラニンは赤茶色~黄色の色素です。髪に含まれるユーメラニンの量が多いと黒色に、少ないとこげ茶色になります。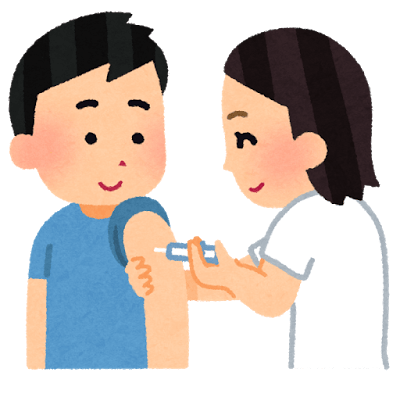
 ペンシルテストの
ペンシルテストの まつ毛のエクステンションもあります。
まつ毛のエクステンションもあります。 【熱による髪へのダメージ】
【熱による髪へのダメージ】