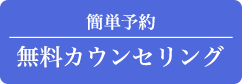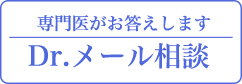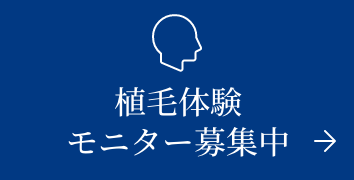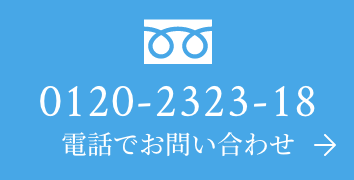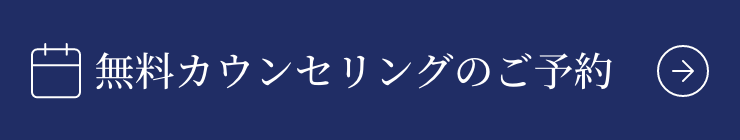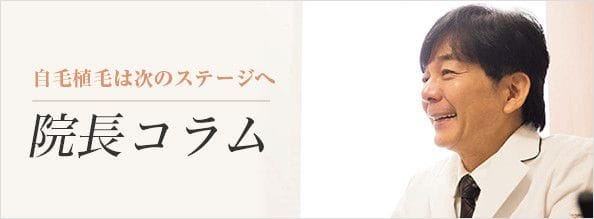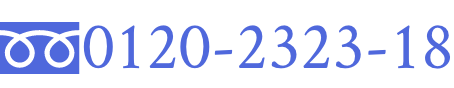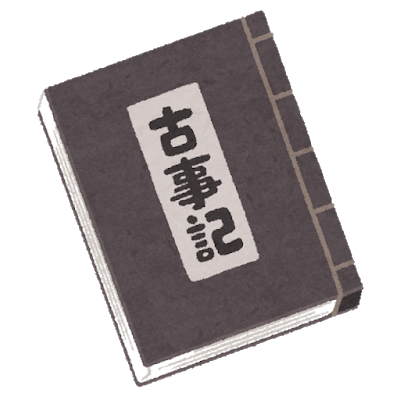自毛植毛の歴史
皆さんは「自毛植毛」についてどの程度ご存知でしょうか。薄毛、脱毛、自毛植毛に関する情報を皆さんにお届けしたいと思います。
自毛植毛がアメリカから日本に上陸したのはもう十年以上前になります。その間にも様々な技術改良や頭髪に関する研究も日進月歩進化し、同時に自毛植毛も更なる進歩を遂げてきました。自毛植毛の最大の魅力とは、正しい手術をし成功した場合その移植した毛髪はそこで生え続けることができます。また、自分の毛髪の移植なのでアレルギー反応が起きる心配もありません。
では、「自毛植毛」の治療について詳しく解説していきましょう。
「自毛植毛」は、毛髪が生える元となる毛根の部分を頭皮に移植することを言います。さらに言えば、人間がもつ皮膚付属器官である毛包の単位で移植をするため、二本から三本の毛の束で移植をすることができます。生着に成功すればそのまま自然の髪の毛のように一生自然に生え続けることができますので術後のメンテナンスは不必要です。
この記事をご覧になっている方の多くは、何かしら頭皮に対して悩みを持った方なのではないでしょうか。
頭髪の薄毛が始まってしまうと、進行を防ぐことはできても自然の力で元に戻すことは難しいと言われています。そんな方に自毛植毛は効果的な治療法といえます。ただ、いきなり自毛植毛を受けようと思っても不安な部分や知らないことが多いことも事実です。
まずは、「自毛植毛」について少しでも皆さんに知ってもらい理解をしてもらうことが必要であると考えています。
今回【自毛植毛データアラカルト】では薄毛・脱毛・頭髪に関する事柄、そして「自毛植毛」について、皆さんが理解できるようストレスのないように解説をしていきたいと思います。
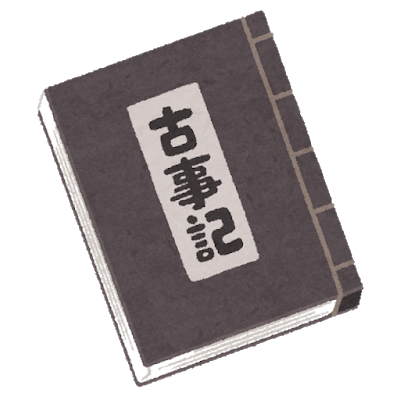
【植毛のはじまり】
現在、日本では自毛植毛の認知度はそれほど高くないと言われていますが「植毛」はとても長い年月をかけて研究され、そしてさまざまな技術が考案されてきました。植毛の技術はアメリカから日本へ上陸してきましたが、どのような歴史を辿ってきたのでしょうか。
そもそも植毛のはじまりは、19世紀末-1983年にドイツの外科医が頭髪や頭皮の移植をしたことからだと言われています。当時、ヨーロッパでは大規模な戦争も多かったために負傷兵への治療のため皮膚を移植する医療技術も取り入れられていました。こうした影響から皮膚移植の進化を遂げ、薄毛対策として、毛髪を移植するという技術が生まれたのだろうと言われています。
【自毛植毛の概念―1960年代】
日本人の医師も自毛植毛について、優れた研究と開発をしてきました。戦争などの理由で世界に広がずに埋もれてしまったと言われていますが、1939年には奥田庄二医師は1939年に「パンチグラフト」の手法を発表しました。この発表により「自身の毛髪をのかの箇所へ移植する」という概念が世に浸透したのです。この発案は常識を覆し自毛植毛への技術進化が進歩するきっかけとなりました。その後、彼の理論は埋もれてしまいますが、後にノーマン・オレントライヒ医師がパンチ・グラフト法を確立した際に、奥田庄二医師の手法が再度、注目されました。
―パンチ・グラフト法とは?
では、パンチ・グラフと法とはどのような植毛技術なのでしょうか。この植毛方法は自毛植毛の原点とも言われています。主な方法は、後頭部からドナーと言われる移植のもととなる部位を採取し、約直径4㎜ほどのグラフトに分けて植えつけます。しかし、パンチ・グラフト法はグラフトが直径3、4㎜と大きく、余計な部分も多いため植毛部位同士の間に隙間ができて地肌が目立ち、術後の仕上がりがとても不自然な仕上がりになるのです。そのため、この植毛方法は全く行われていませんが、当時は唯一の植毛法だったためにパンチ・グラフト法なくして現在の自毛植毛はない、と言えるほど自毛植毛の原点となり、多大な影響を与えたのです。
【植毛の発展期=1970年代】
植毛自体は、1960年代に始まったとされていますが、自毛植毛の「毛根がある皮膚を切り取って、植毛が必要な部位に移植する」という現在の「自毛植毛」に近い技法が1970年代から用いられるようになりました。それまでの植毛法は移植する皮膚の幅が約10㎝と大きく切り取っていたため術後の仕上がりが不自然だったことがデメリットでした。しかし、1970年代は切り取る毛根の幅を株(グラフト)単位で切りとる技術が発達したため術後の仕上がりが自然で目立たなくなったと言われていました。また人工の毛髪を移植するという「人工植毛法」も1930年代に始まったと言われていますが頭皮に異物を埋め込むわけですから異常反応が起こったり痛みなどが生じてしまうこともあり現在はアメリカやなどで手術自体が禁止されています。1970年代前半に「フラップ法」が開発され、70年代後半には「スカルプ・リダクション法」が開発されました。
―フラップ法とは?
1970年代前半に開発された「フラップ法」という植毛法とはどのような植毛法なのでしょう。薄毛の方の場合、人によっては側頭部に頭髪が多く残っている場合があります。この部位の一片をフラップと呼びます。このフラップだけを毛根から切り取り移植する方法です。フラップを切り出す方法も様々な方法が考案されましたがこの方法には難点がありました。移植した植えつけの髪の向きの調節が難しいため見た目が不自然になってしまうのです。また、失敗してしまった場合血流をうまく巡回させることが難しく、移植したフラップが全て懐死してしまう危険性が問題視されていました。
―スカルプ・リダクションとは?
1970年代後半に入ると「スカルプ・リダクション法」という植毛法が開発されました。これはフラップ法と同じように頭皮を切り取って移植する方法になりますが、切り取る部分は薄毛部分で周囲を引っ張り縫い合わせることで薄毛の箇所を改善するという方法です。手術時間も短時間で済みましすし、術後すぐに見た目も改善されているために関心を集められていました。ただ、「スカルプ・リダクション法」の施術患者の中には切り取った頭皮の周囲部分の抜け毛が多くなるというような副作用の事例が多く見られました。その副作用を「ストレッチバック」と呼びます。頭皮を引っ張り縫い合わせたために血流が悪くなり、酸素や栄養が行き届かなくなったことが原因だと言われています。
【自毛植毛術の進化=1990年代】
1990年代に入り、自毛植毛の技術や開発に力を注ぐ研究者たちも増え、術後の仕上がりも考慮した様々な方法が開発されるようになりました。中でも、FUT法やFUE法などの自毛植毛の技術は現在でも多く用いられています。また、生え際の植毛の際には仕上がりを美しくするために、毛根を細かい単位で移植できるような技法が取り入れられ、グラフトはミニグラフトからマイクログラフトまで進化をしました。
―FUT法とは?
毛細単位植毛(FUT法)は現在世界的に行われている植毛技術です。FUT法は、今までの植毛技術を進歩させたものになりますが、植毛をする際に毛穴から生えている毛根を1本ではなくまとまりの株をそのまま移植させようとした方法です。このFUT法が広まったことでこれまで行われていたフラップ法、パンチグラフト法のデメリットである仕上がりの不自然さが改良されました。現在の自毛植毛術でも活躍している方法で、大量の植毛をしたい方に向いた術式になります。
―FUE法とは?
植毛には毛根を移植をしますが、髪にメスを入れない方法も存在します。それをFUE法と呼んでいますが、植毛を希望している方野中に、切らないで植毛をしたいと希望している方や頭皮をメスで切り取ることができないような方もいらっしゃいます。FUE法でしたらメスで切らない手術ができる可能性があります。
その為FUT植毛は術後の仕事復帰なども早く出来る可能性があります。
切らない施術とは、メスを使わずに毛穴をくり抜く方法のことを言います。くり抜いた箇所は術後縫わずに傷がふさがるのを待つことになります。髪が長い方は目立たないのですが短髪などの短い髪形ですと傷跡が見えることがございますが、最近は傷跡を小さくする機材も増えていますので、以前より目立ちにくくなってきています。
また、FUT法に比べて同じ面積から多くのドナーを取ることができません。大量の髪を植毛したい方には向いていない方法と考えられています。
【新たな植毛術(医療としての頭髪再生)=2000年代】
2000年代以降から今日まで、様々な薄毛対策が開発されていますがかつての植毛法と比べると著しい進歩を遂げています。以前の植毛法で問題視されていた点に関しても近代の自毛植毛技術の発展によって満足度の高い植毛技術が提供できるようになりました。毛髪を再生するための医療行為としては、内科的方法の薬を服用する医療行為と外科的方法である頭皮を移植する医療行為のふたつがあります。
現在も植毛法についての研究も進んでおり確かな効果があり、リスクを回避できる施術が受けられる時代ともいえるでしょう。
【現代の植毛(女性への薄毛対策の進歩)=2010年代】
現在の植毛技術は、医師達の経験、実績を基盤として研究、開発を行い非常に精度の高い植毛法が編み出されてきています。自毛植毛を受けたいという方の中には頭皮を移植するということに不安を持つ方もたくさんいます。そんな方でも安心して施術を受けられる“メスを使用しない自毛植毛法”も開発されていますし、さらに改良されたハイブリット自毛植毛≪i-SAFE≫なども開発されています。
また技術の向上と共に大量の植毛を行うメガセッションや、FUTとFUEの良いところを組み合わせたハイブリッド法など、自毛植毛の進歩と共に各院の独自の術式名が増えております。
また、女性のための植毛法も男性の植毛の歴史と比較すると歴史は浅いですが、現在では飛躍的にレベルアップをしています。以前は、男性用の薄毛治療の薬を女性にも使用していたこともあったと言われていますが、男性と女性では毛髪の生えるメカニズムが違いますから効果もなく、副作用の危険性もありました。ここ近年では、女性のための薄毛治療のクリニックも増え、女性へ向けた薄毛対策の研究も進んでいます。
 紫外線とは、太陽から放出される太陽光線の成分のひとつ。肉眼では見ることが出来ない「不可視光線」です。紫外線は、可視光線(目に見える光線)よりも波長が短く、またX線より長い電磁波。 地球の表面に届く太陽光線全体の中の約6%ほどと言われています。
紫外線とは、太陽から放出される太陽光線の成分のひとつ。肉眼では見ることが出来ない「不可視光線」です。紫外線は、可視光線(目に見える光線)よりも波長が短く、またX線より長い電磁波。 地球の表面に届く太陽光線全体の中の約6%ほどと言われています。 日焼け止めの使い方
日焼け止めの使い方